『ロジカル・プレゼンテーション』は、提案を通すための考え方と伝え方がわかる本。
論理思考力・仮説検証力・会議設計力・資料作成力がストーリーに沿って理解できます。
提案は意図して通すもの。通らない・伝わらないのは伝え方が悪いからであり、考えていないことはうまく伝えることができません。
★ 『ロジカル・プレゼンテーション』 の要約ポイント★
・論理思考力で縦の論理と横の論理を通す
・仮説検証力の5ステップ
①目的を理解する
②論点を把握する
③仮説を構築する
④検証を実施する
⑤示唆を抽出する
![]()
この記事では 『ロジカル・プレゼンテーション』 の要約を紹介します。
『ロジカル・プレゼンテーション』 はAmazonAudibleの無料体験で読めます。
✅30日間の無料体験で何冊でも聴き放題!
✅月額1500円(ビジネス書1冊で元が取れる)
✅手が離せないときに耳から学習できる
目次
要約①:論理思考力で縦の論理と横の論理を通す

論理思考力は、どんな人にも話を伝えるために必要です。
人はそれぞれ価値観が違う、文化が違うからこそ、論理思考力がなければ話のつながり示すことができません。
論理的かどうかを決めるのは受け取り手のほうです。「あの人は論理的でないから話が伝わらない」と相手のせいにするのではなく、どんな相手でも伝えられる人が論理思考の高い人と言えます。
論理には2つあります。
・縦の論理=因果関係
・横の論理=MECE(漏れなくダブりなく)
縦の論理=因果関係
縦の論理は因果関係です。AならばBがスッと理解できると、縦の論理が通っていることになります。
縦の論理が通ってないと「本当にそうなの?」と疑問を持たれてしまいます。
縦の論理がつながらない原因は3つあります。
・前提条件の違い:「AならばB」の前提が共有されていない
・異質なものの同質化:違うものをひとくくりにしてしまう
・偶然の必然化:「AならばB」はたまたまなのでは?
前提条件の違いは、聞き手によって暗黙の前提や背景が共有されていなかったり、自分が前提を思いこんでいたりすると起きます。自分の前提を疑い、前提を知らない人や価値観の違う人に話してみて伝わるかを確認しましょう。
異質なものの同質化とは、本来違うものを同じ前提にして結論を導き出してしまうことです。たとえば、「〇〇市場は拡大するので投資すべき」と言ったとき、聞き手が「〇〇市場と言っても細かく見れば全然違う」と思えば、「本当にそうなの?」という疑問が浮かんでしまいます。特に自分の詳しくない領域は解像度が低いためにざっくりひとまとめにしがちです。
もっとこまかく見る必要がないか?本当にひとくくりにしてよいか?と確認しましょう。
偶然の必然化は、たまたまのことを必然のように結び付けてしまうことです。「この商品は絶対に売れます!」と言うほうは売れるまでのプロセスを必然と考えていますが、聞き手が「売れる・売れないは偶然」と考えていれば「本当にそうなの?」と感じるでしょう。
自分が必然だと思う「AならばB」を、時系列の流れに沿ってなるべく否定的に考えてみましょう。「AならばB」を妨げる要因に説明がつかなければ、納得させることはできません。
横の論理=MECE(漏れなくダブりなく)
横の論理はMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive:漏れなくダブりなく)になっていることです。
漏れがあったりダブりがあったりすると、横の論理が通ってないと「それだけなの?」と疑問を持たれてしまいます。
横の論理がつながらない原因は、言葉のレベル感がズレていることが多いです。
漏れなくダブりなくを確認する以前に、そもそも違う話をしていないかを確認します。次元の違う話は言葉のレベル感をそろえ、その後に漏れなくダブりなくを考えます。
言葉のレベル感が揃わないのは、視点の違い・切り口の違いが原因です。
・視点の位置を揃える:事業責任者の視点、営業の視点など誰の言葉か
・切り口を揃える :どういう場面を想定した言葉か
漏れなくダブりなくを実現する手軽な方法はフレームワークを使うことです。3C分析、5フォース分析、PDCA、7Sなど、既存のフレームワークは使えばMECEになるようにできています。
しかし、既存のフレームワークにこだわり過ぎて、使う場面を間違えないようにしましょう。いつでも既存のフレームワークが使えるわけではないので、自分でMECEを考える力も必要です。
要約②:仮説検証力の5ステップ

いくら主張が論理的でも相手が納得しないことがあります。それは、相手の疑問に答えていないときです。相手の知りたいこと、問題意識を理解せずに正しいこたえを用意しても、それは価値を生み出しません。
相手の疑問=論点を洗い出し、疑問に対する答え=仮説を検証することが必要です。
<仮説検証力の5ステップ>
①目的を理解する
②論点を把握する
③仮説を構築する
④検証を実施する
⑤示唆を抽出する
1つずつ紹介します。
①目的を理解する
ここで言う目的とはコミュニケーションの目的であり、議論のスタンスと相手の要望を理解します。
どういうスタンスで話をすればいいのかは変わります。
・意志判断をしてほしい:報告、プレゼン、ディスカッションなど
・話を聞いてほしい:雑談、愚痴、何気ない会話など
スタンスを見誤ると、愚痴を聞いてほしいだけなのに結論がなくてイライラする、意志判断を迫られてうっとおしい等のすれ違いが起きます。相手はどちらのモードで、自分はどちらのモードを求められているのかを意識しましょう。
提案は意志判断をしてほしいことが多いでしょう。そのときは具体的な話(担当部門と作業スケジュールなど)で締めくくることで話を進めます。それにより、何に対して意志判断をしてほしいか明確になります。
相手の要望を理解するのは、相手の言葉や表情から感じ取るアナログなスキルです。相手の話を聞くこと、気配りをすることも提案を通すためには欠かせません。
②論点を把握する
論点とは、相手の意志判断に影響を及ぼす判断項目のこと。
論点を外さないために、論点を外す4つのパターンを知っておきましょう。
<論点を外す4つのパターン>
・スタンス違い:意志判断を求めていない
・要望のくい違い:相手の要望を理解できていない
・具体的な判断項目が出せない:横の論理がつながっていない
・答えを持っていることを繰り返す:相手にとって当たり前
この4つのパターンのうち、何がうまくいっていないのかを把握することで、論点をかみ合わせるために必要なことがわかります。
スタンス違い、要望のくい違い、相手の当たり前を理解するのはアナログのスキルです。論点を把握するには、相手の話をよく聞くこと。論理思考だけでは論点を把握することができません。
③仮説を構築する
仮説は論点に対する山勘の答えのこと。つまり、論点あっての仮説であり、論点をつねに頭に入れて仮説を構築する必要があります。
論点に対してすべての選択肢を検討するのは効率が悪いです。仮説を持つことで、検討の効率を上げることができます。
仮説は次のステップで構築します。
・論点をしっかり頭に入れる
・答えは何かを考える
・とにかく多くの情報をながめる
仮説は山勘とはいえ、何の根拠もない当てずっぽうではありません。仮説は無からは生まれず、たまたま持ち合わせている情報から生み出します。
仮説を出すための情報収集は日頃から集めている広く一般的な情報です。一方、仮説を検証する際は仮説を証明するための狭くて限定的な情報になります。仮説構築のための情報収集が、いつの間にか検証の情報収集にならないように気を付けましょう。
仮説の精度を高めて量を出すには、論理思考の縦横の論理を使うのがポイントです。
横の論理を広げて「他にはないか?」と考えればいろいろな角度から仮説を出せますし、「本当そうなの?」と疑うことで精度が高まります。
④検証を実施する
仮説を検証をするには、客観的な事実と論理が必要です。
ここまでやれば検証は十分だ、というのは相手が決めるため、相手が納得するまで検証は終わりません。
検証のコツは強いファクト(事実)を入れることです。
・定量情報ー定性情報:測定可能か
・一次情報ー二次情報:直接集めたか
・第三者情報ー当事者情報:外部機関が調査したか
定量情報は数字に代表される測定可能なデータであり、定性情報は感想など主観的な情報です。定量情報のほうが主観が入りにくいため強いファクトと言えます。
一次情報は直接集めた情報、二次情報は新聞やメディアなどがまとめた間接的な情報です。第三者情報は外部機関が調査した情報であり、当事者情報は社内関係者の調査結果などがあたります。
強いファクトは定量×一次×第三者情報です。説得力を増すため、検証結果にできるだけ強いファクトを入れましょう。
⑤示唆を抽出する
示唆とは論点を絞り込むために役に立つ情報です。
相手の疑問への答えが出れば一番良いのですが、実際のビジネスでは直接答えを導き出すファクトや論理を揃えるのが難しいでしょう。だから、現実的には論点を絞り込む示唆が結論になります。どこを深掘りすれば答えが出るかわかるだけでも価値があります。
示唆を出すための3つのポイントは次のとおりです。
・目的と論点を理解する:そもそもなんの作業か
・論点の絞り込みに集中する:相手が最も知りたいのは何か
・検証不能な作業設計をしない:情報を集められるか
目的と論点を理解することで、仮説そのものが検証できなくても、他の仮説をひねり出すことができます。検証を作業ベースで行っていると、この作業ができた/できなかったという視点しかないので、それ以外の示唆が出てこない・言われたことしかやらないと思われてしまうかもしれません。
相手が最も知りたいことに集中し、どこにファクトを示せばいいかを絞ることで、効率的にインパクトの大きい示唆を示すことができます。
こまかすぎる情報、広すぎる情報、未来の情報など集められない情報が必要な場合は検証ができません。データの有無の感覚を鍛え、「そもそもそんなデータは取れるのか?」を確認しましょう。
このあとに会議設計力、資料作成力と続きます。本には具体例もたくさん載っているので、おもしろそうだと思った方はぜひ読んでみてくださいね。
『ロジカル・プレゼンテーション』 を無料で読む方法

『ロジカル・プレゼンテーション』は耳で聴けるオーディオブックがあります。
Amazon Audibleの無料体験を活用すれば無料で読むことができます。
いつでも解約が可能です。無料体験中に解約すればコストはかかりません。
⇓⇓登録手順や解約手順はこちら!
【Amazon Audibleの無料体験はかんたん】12万冊以上の本が聞き放題で効率的に読書できる
『ロジカル・プレゼンテーション』 の次に読むなら?
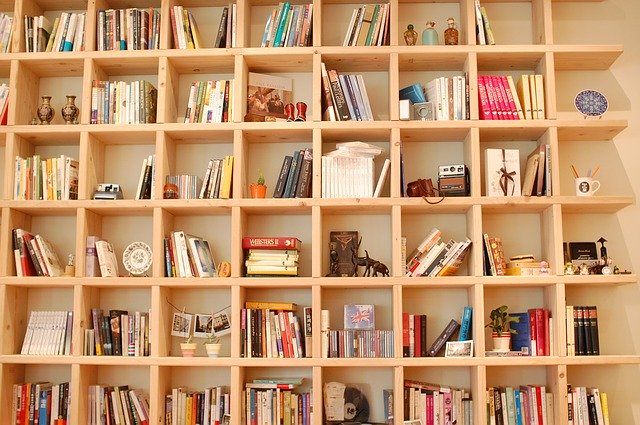
『ロジカル・プレゼンテーション』 とあわせて読みたい3冊を紹介します。
①『問題解決―あらゆる課題を突破する ビジネスパーソン必須の仕事術』
『問題解決』は、『ロジカル・プレゼンテーション』の著者が問題解決の定番教科書をイメージして書かれた本。
問題解決の手順をWhere⇒Why⇒Howの順で進めていきます。
Whereでどこに問題があるのかを明確に設定し、Whyで広く深く掘り下げます。
参考記事:【本の要約】『問題解決-あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術』
②『仮説思考』
『仮説思考』は複数の選択肢の中から仮説→検証を繰り返して最良のものを選び出す思考法です。
仮説を立てることで、必要最小限の情報で素早く最善の選択ができます。
参考記事:『仮説思考』の要約まとめ:速くて質が高い仕事をするには仮説思考を鍛える
③『実践型クリティカルシンキング』
目標を達成するために使える、クリティカルシンキングの3STEPが講座形式でわかる本。
STEP1:目指すものを定義する
STEP2:何が問題なのかクリアにする
STEP3:打ち手を考える
解決方法を考えるよりも、目指すものや問題そのものを明確にするほうが重要です。
参考記事:『実践型クリティカルシンキング』の要約まとめ:目指すものを達成するための3STEP
★今回紹介した本★
★読書好きな人におすすめのサービス★
・Amazon Kindle Unlimitedで電子書籍を無料体験
・Amazon Audibleで聴く読書を無料体験
電子書籍で多読したい!人にはAmazon Kindle Unlimited!
定価より安くてコスパがいいです。
時間がないけど読書したい人にはAmazon Audible!
手が離せないときにも耳で読書できます。
![]()
無料体験後はいつでも解約可能です!
⇓⇓登録手順や解約手順はこちら!
参考記事:【Amazon Audibleの無料体験はかんたん】12万冊以上の本が聞き放題で効率的に読書できる
★さくっとインプットしたいなら本の要約サービスflier(フライヤー)★
読み放題のゴールドプランが7日間無料で試せます。
参考記事:本の要約サービスflier(フライヤー)の料金プランはどれがおすすめ?【お得に試せる】
本業の会社員では研修講師やファシリテーターをしています。コーチングも提供しているので興味がある方はぜひご検討ください。
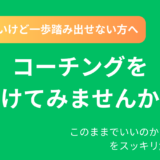 自分を信じて行動が続けられる方法:コーチングを受けてみませんか?
自分を信じて行動が続けられる方法:コーチングを受けてみませんか?


