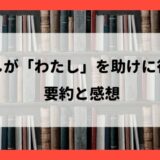コーチングに興味を持っている方、コーチングを学ぼうと思っている方の参考に、わたしのコーチングの学習過程を紹介します。
振り返れば、やらなくてよかったと思うこともありますが、すべての経験があって今がある、と前向きに捉えています。
現時点で最も効果的な学習方法だったと思うのは、意図を持った実践です。つまり、1つ課題・テーマを持って、それを練習セッションのなかでやり切って振り返る。この繰り返しが、一番効果的だったと感じています。
とはいえ、コーチングは一生学習だとも感じており、のちに点と点がつながるかもしれないので学習の過程を残しておこうと思い立ちました。
コーチング学習のお役に立てば幸いです。
目次
コーチングの出会いは社内研修
まずコーチングに初めて出会ったのは社会人4年目の社内研修でした。新入社員の相談相手(メンター)に課せられた研修のなかでコーチングを学びました。
しかし、今思えばこれはコーチングのほんの触りだけ。オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの違いや「なぜ」は問い詰めるから他の疑問詞に変えようとか、Iメッセージでフィードバックしようとか。。。
あくまで日々のビジネスコミュニケーションにコーチングの技術を取り入れるというものでした。
それが悪いわけではないのですが、起業のコーチング研修のイメージでコーチングスクールに行くと、ギャップを感じることになりそうです(ビジネスコーチングに特化しているスクールならギャップは少ないかも)。
その後、コーチングの本を数冊読み、社内の面談でGROWモデルを使うなど、なんちゃってコーチングのコミュニケーションを繰り出していました。それはそれで効果があった場面もあります。でも、今振り返ればそれはコーチングではありませんでした。
ザ・コーチ・アカデミーで学ぶ
時は流れて、2022年に組織風土改革を担当する部署に異動となり、そこでコーチングを勧められます。組織風土を変えるには、強制ではなく、内側からのエンパワーメント、自分からやりたくなることが重要という理由からです。たしかにそう、と思って、まずはザ・コーチ・アカデミーの基礎コを受講しました。
たくさんのコーチングスクールがあるなかで、なぜザ・コーチ・アカデミーを選んだかというと、費用が安かったからです。会社の経費で受けたので、正直なところ、一括100万円オーバーのスクールは選べなかったんですよね。
あと、なんとなくビジネスゴリゴリのコーチングよりも自分が苦手な直感を使う系のコーチングのほうが、経験値として取れ高が高い気がしました。まだ伸びしろがあるというか。結果的に、その選択は良かったと思っています。
ザ・コーチ・アカデミー(基礎コース)
基礎コースは、会社員の方が仕事で活かそうという方が60%、コーチングで独立や副業を考えている方が20%、自分が悩んでいてコーチングを受けて興味を持った方が20%くらいの参加者属性でした。もちろん、回によって変わるので、あくまで私が参加した回の印象です。
ザ・コーチ・アカデミーで学習する中身は書けませんが、コーチング初心者が戸惑いながら実践しながら、モヤモヤしたものを抱えながら進む感じです。
知識という面では、本で読んだことがある・聞いたことがある内容で、これを聞けば絶対気づきを促せる魔法の質問などはないです。正解がないなかで、モヤモヤしながら、そのモヤモヤを一緒に受けている人やリード(先生)と共有することで、ちょっとずつ掴んでいく感じでした。
どんな人と一緒に受けるか、ペアワークで誰と当たるかでも受け取れる価値が変わるかもしれません。コーチングをどれだけ知っているかに関係なく、誰かのふとしたひと言が、妙に心に残ったりして内省が深まっていきます。
3日間受けたらモヤモヤが晴れるのかというと、そんなこともありません。でも、コーチングを学習するとはそういうことなのだな、というのだけはわかりました。つまり、終わりがない、誰も答えを教えてくれない、自分の器(受け入れる力とか信じられる力とか)が試されるし、そのまま出てしまうものなのだ、と理解しました。
たぶん、答えがないならやめておこう、という人はここで学習を終える気がします。それはその人の選択で良い・悪いはないです。むしろ、沼にはまるのを避けられる点では賢明な判断といえるかもしれません(笑)
わたしが基礎コースで学んだ・感じたことは、次のとおりです。
・バイアスにとらわれないでフラットに話を聞くのは得意(どちらかというとマイノリティな考え方だから)
・左脳・論理はよく働くが、それだけではうまくいかない領域がある
・わたしは右脳的なイメージや直感を使うのが苦手だ
・でも、イメージや直感も使って人の役に立てる自分になりたい
ザ・コーチ・アカデミー(応用Aコース)
基礎コースに続けて、応用Aコースを受けました。こちらはリソースフルコーチングと呼ばれているタイプのコーチングを学習するコースです。
けっこうイメージや直感を使うので、とても感動している人がいる一方、モヤモヤしている人もいて、若干のカオスを感じました。受け取り方、感じ方は千差万別で、そこに人の心のおもしろさも感じます。
ここでサブパーソナリティという概念を学びます。サブパーソナリティはザ・コーチ・アカデミーのオリジナルではなく、統合心理学に出てくる概念です。
サブパーソナリティ:異なるパーソナリティを持つ、内なる自分
自分に厳しい長官のサブパーソナリティがいるな、羽目を外したい子どものサブパーソナリティがいるな、など、自分のサブパーソナリティを見つけるのにハマります。
サブパーソナリティという言葉を使っていなくても、自分のなかのいろいろな私という概念は、心理学やカウンセリングのいろいろな本に出てきます。
(参考記事)『わたしが「わたし」を助けに行こう』の要約と感想
(参考記事)『私とは何か』の要約まとめ:分人主義という人間観に救われる
応用Aを学んでから、自分のサブパーソナリティと(心の中で)会話するというセルフコーチングができるようになりました。これは応用Aで学んで一番良かったことです。
また、セッション練習でペアになった方に、「一緒にダンスできた、セッションになっていた気がする」と感想をいただいてとてもうれしかったです。「コーチング、向いているかもな」と思えました。
わたしが応用Aコースで学んだ・感じたことは、次のとおりです。
・自分の中にいろんな人がいることに気づく
・自分の嫌いな部分にも、存在理由がある
・ビジョンを考えると少し心が温かくなる(少し直感や身体感覚がわかってきたかも)
また、毎回の授業の後に放課後タイムがあり、一緒に受けた同期の方と話せるルームと講師の方に質問できるルームがあります(基礎のときもありましたが、そのときは参加できず)。
わたしは毎回講師の方のルームに行って質問していたのですが、その時間も授業と同じくらいに有意義でした。ぜひ勇気を出して講師のルームに行くのをおすすめします。
ザ・コーチ・アカデミー(応用Bコース)
応用Aコースから続けて応用Bコースを受けました。間を空けても良いのですが、続けて受ける方が半数以上だったので、応用Aから顔見知りの方と受けられるというメリットがあります。
応用Bはビー・ウィズコーチングというタイプのコーチングを学びます。これは感情に留まるのが最重要課題で、個人的にカウンセリングに近いアプローチだと思いました。
目標を立ててガンガン進むのが基本姿勢のわたしにとって、最も苦手分野でした。感情に留まって深く感じた後に必ず浮上するタイミングが来る、と信じる力が試されているようで、せっかちさんにはもれなく試練です。
一番モヤモヤしたのも一番学びがあったのも応用Bでした。コーチングのスキルというよりも、ネガティブ感情の対処の仕方がアップデートされて精神的な成長・進歩を感じました。自分の精神的成長がコーチングの場にも影響するので、結果としてコーチングの学習にもつながったと思います。
今までは、ネガティブ感情を感じたら有益なフィードバックだけ抽出してすぐ捨てる、すぐ捨てなければならないという切迫感があったのですが、留まって感じて自然と立ち上がってくるのを待つ感覚がなんとなくわかりました。必ず立ち上がる瞬間が訪れると自分を信じる強さがあるから、そこにあるものを見に行けるのだと今は思っています。
わたしが応用Bコースで学んだ・感じたことは、次のとおりです。
・感情に留まる価値、感情に向き合えるのは自分を信じられているから
・場をホールドする、沈黙していてもそこにいる安心感
・下手するととんでもないトラウマに触れてしまう危険性もある、それだけパワフル
練習あるのみ!相互セッションで経験値を積む
コーチングスクールでの学びもひと段落終えて、ここで気づいたことは経験値が足りないという事実。新しい知識も大切ですが、けっきょくインプットしても自分のものになっていなければ意味がない。
そこで、コーチングできる場に積極的に参加することにしました。
<コーチングの機会を増やすためにやったこと>
・ザ・コーチ・アカデミー内の月2回の練習にフル参加
・不定期の練習相手募集に参加
・知人、友人にコーチング
・スクール外のコミュニティに参加して相互セッション
・社内でコーチング募集 など
スクール内コミュニティで練習するデメリット
まず取り組みやすかったのが、コーチングスクール内での月2回の練習です。もちろん学びも多く、今でも参加しているのですが、次第に課題にぶつかります。
コーチングスクール内で練習するデメリット
・セッション時間が15分と短い
・コーチ同士、しかも同じものを学んでいるので、うまくいってしまう
もし副業や専業でコーチングをするなら、30分~60分のセッションが一般的です。15分だと途中で終わってしまうので、具体的な行動に落とすところまでたどりつけないことが多く、そこの経験値が積めません(必ずしも行動に落とさなくてもよいのですが)。
また、コーチ同士なので基本的に内省力が高く、いまいちな質問でも「こういうことが聴きたいのだろうな」と善意で意図を補って進んでしまう感覚がありました。
スクール外コミュニティでの練習
そこで、スクール外のコミュニティに参加します。わたしはfacebookの相互セッションやモニター募集のグループに参加しました。
コーチングといっても、スクールによって元にしている理論や流派が違うので、全然アプローチの仕方が違います。クライアントとして体験できるのも、とても学びになりました。
オーソドックスなGROWモデルのアプローチの方もいれば、タイムラインや身体を動かすなどNLPが強めだったり、認知科学で10倍大きなゴールを考えてみたり…
学んだスクールが違うので、質問の伝わりやすさが全然違います。同じスクールではスッと通じた質問が、外の世界では伝わらず…ということは、コーチングをまったく学んでいない人にはもっと伝わらないので、相手を見ながら伝わる質問に調整していく練習ができます。
社内でのコーチング提供
社内でコーチングを受けたい人を募集し、希望者にコーチングをしました。そもそも会社のすすめでコーチングスクールに行ったので、「社内でコーチングを受けたい人を募集していいですか?」と言いやすかったです。会社への貢献ということにすれば、評価も得られるので一石二鳥。会社員の方にはぜひおすすめのやり方です。
数名が手を挙げてくれたので、コーチングセッションを提供しました。ここで感じた課題は、会議室でやるとどうしても日常から出られないということ。できれば会社から離れた環境を用意できると良いです。
論理的であること、わかりやすく話すことなど、普段仕事で求められることが自分と向き合うときに邪魔になることがあるので、少しでも仕事から切り離した環境がつくれると入りやすいと感じました。
初めての有料セッション
相互セッションも練習になりますが、お金をいただいてセッションするのはまた違った緊張感があります。はじめての有料セッションは知人に受けていただきました。やはり、オフラインのつながりのほうが信頼を得やすいですね。
最初は、コーチングとは何か、コーチングの受け方など10分ほど説明してからセッションに入りました。このあたりの説明ももっとブラッシュアップしなければ…実際にクライアントを目の前にして説明すると、こなれていない感が出てしまいます。
最初の有料セッションは、「自分がなんとかしなければ、気づきを得てもらわなければ」が強く出過ぎて反省点が多かったです。練習セッションと全然違った!と感じたので、早くから少額でもお金をもらってセッションすることをおすすめします。
効果的なコーチングの学習方法
今時点で最も効果的なコーチングの学習方法だと思うのは、意図を持った実践です。1つ課題・テーマを持って、それを練習セッションのなかでやり切って振り返る。
具体的には、次のように取り組んでいます。
・過去のコーチングの振り返りメモを見る
↓
・今日の練習セッションで取り組むことを1つ決める
↓
・相手がコーチの場合、セッション前に取り組むことを1つ宣言し、その観点でフィードバックをもらえるように依頼しておく
↓
・練習セッションをする
↓
・フィードバックをもらう
↓
・録画/録音で振り返る
練習セッションの良いところは、実験ができることです。自分が向き合いたいことを1つ決めて、それをやり切って振り返ることで、徐々に感覚がつかめてきます(が、直線的な成長ではなく、いったり来たりします)。
たとえば、わたしが取り組んだテーマ例としては次のようなことがあります。
・表情や声のトーンを反映する
・比喩やイメージを使う
・感情に留まる
・自分の感じたことをフィードバックしてどう感じたか聞く
・自分の声のトーンや話すスピードに変化をつける
・最後にアクションを立てる
・アクションへの本気度を確認する など
テーマや相手の反応によっては使うタイミングがなかったりしますが、何か意識を持つことは重要だと思います。「とにかく量だ!」と思って漫然と練習セッションするより、今の自分の課題は何か?を考えて、それにフォーカスした練習はとても学びが多かったです。
特に試したいことがあるときは、練習セッションを募集するときにテーマを絞って募集します。
たとえば、目標設定したい人/人間関係でモヤモヤがある人/価値観を棚卸ししたい人など、ある程度テーマを絞ると、自分が練習したいことと関連度の高いテーマである確率が上がります。とはいえ、セッションはその時々でどうなるかわかりませんが。。。
セッションが通算50時間を超えたとき、意識の変化がありました。
それまでは「自分が受けとめきれないテーマが来たらどうしよう」「役に立てなかったらどうしよう」という不安がありましたが、今は「どんなテーマが来ても、受けとめることはできる」、「自分にできることを全身全霊でやるだけ」と思えるようになりました。
まとめ:コーチングの学びは続く
コーチングは終わりのない学び、沼です。でも、沼から出たときにはきっと人間的に成長していて、そして、またそこに沼がある。そんなイメージを持っています。
終わりがないこと、正解がないことに取り組むのはストレスもありますが、ずっと情熱をもって取り組めることを見つけられた喜びもあります。
もしコーチングに興味をもってここまで読んでくださったのなら、コーチング沼にようこそ!と言いたいです(笑)
本業の会社員では研修講師やファシリテーターをしています。コーチングも提供しているので興味がある方はぜひご検討ください。