第29回キャリアコンサルタント試験に合格しました。
合格までの道のりは長く、キャリアコンサルティング協議会で学科合格・実技不合格になった後、2年間この試験から離れ、JCDAで実技のみリベンジして合格しました。
2年間のブランクがあるのは、実技不合格の理由がわからず、この資格の価値がわからなくなったからです。ですが、2年間のブランクの間に転職し、そこで社内カウンセリングを行う話が出てきたので再度挑戦しました。
2025年現在、合格率60~70%ほどの試験ですが、その数字の印象ほど簡単な試験ではないです。特に実技のロールプレイは採点基準が不明確で、相談者役・試験官に当たり・ハズレがあるとも言われています。
そんな理不尽さも受け容れつつ、できることをやるしかないので、これから受験する方に向けて役に立てばと思い、おすすめの勉強方法とやってよかったことをまとめました。
どなたかの参考になれば幸いです。
目次
キャリアコンサルタント試験おすすめの勉強方法:学科編
学科は100点中88点(50問中44問正解)で合格しました。学科で外せないのは以下の3つです。
・キャリアコンサルタント試験の過去問
・キャリアコンサルティング技能検定2級の過去問
・統計資料の学習
1つずつ紹介します。
キャリアコンサルタント試験の過去問
キャリアコンサルタント試験の過去問は最新3回分しか公開されていないので、受験を考えているならすぐにダウンロードしておきましょう。論述の問題も一緒にダウンロードしておきます。
わたしは養成講習に申し込んだときからダウンロードし、手元に直近5回分はありました。もし、もうすでに過去分はダウンロードできない時期なら、養成講習の仲間にお願いすると持っている人がいるかもしれません。
キャリアコンサルタント試験の過去問、最低でも直近3回分は100点が取れるまでやり込みましょう。できれば5回分あると良いです。統計はその当時の問題なので、どんなことが聞かれるのか出題傾向だけ確認すればよいです。
キャリアコンサルティング技能検定2級の過去問
キャリアコンサルティング技能検定2級の学科試験はキャリアコンサルタント試験と試験範囲が同じです。
キャリアコンサルティング技能検定2級で出た問題がキャリアコンサルタント試験に出ることもあるので、試験は違えどとても参考になります。
キャリアコンサルタント試験の過去問と同じく最新3回分しか公開されていないので、受験を考えているならすぐにダウンロードしておきます。
個人的な印象ですが、キャリアコンサルティング技能検定2級のほうが理論家の出題が多く、よりマイナーな先生(と言っては失礼ですが)が出てくると感じました。
こちらも100点が取れるまで何周もします。こちらはダウンロードのタイミングが遅く、わたしは最新3回分で100点が取れるまでやりました。
統計資料の学習
統計資料の学習はどの資料から何が出るかわからないので、一番やりにくかったです。鉄板の資料と言われるものに目を通り、自分の当たり前と反する箇所を中心に覚えておきます。
・労働経済の分析
・能力開発基本調査
・賃金構造基本統計調査
・労働力調査
・一般職業紹介状況
・男女共同参画白書 など
経験している業種・職種により、当たり前に答えられるところとそうでないところがあるので、「初めて知った」、「意外だな」と感じるところを印象に残すイメージでした。
よく読めば常識的に判断できる選択肢もあるので、知らないところが出た!と慌てずに、完璧を目指さないのが重要だと思います。
統計資料をやり込むよりは、過去問をやり込むほうがおすすめです。
わたしはインプットするものを1つに絞りたいので、やり込んで学んだことは養成講習のテキストに書き込んでいました。
スキマ時間で学ぶにはかさばるので、そのとき集中して覚えたいものだけを紙に抜き出して反復し、覚えたら紙を捨てる、を繰り返しました。
その他おすすめの学科勉強法
過去問と統計資料が第一優先ですが、まだ時間がある人や苦手分野がある人におすすめの勉強法を紹介します。
労働法が苦手な人向け:社労士の入門書を1冊読む
労働基準法や労災法、雇用保険法、育児介護休業法など労働法が苦手分野の方には、社労士の入門書(薄くて読みやすいもの)がおすすめです。
↓たとえば、こんな感じのもの
わたしは先に社労士を取ったので、労働法は得点源になって楽でした。社労士の問題と比べると、キャリアコンサルタント試験の労働法は本当に基本的なことしか出ないので、社労士のさわりだけ知っておくとだいぶ楽に解けます。
(年金など範囲外のところは飛ばす)
理論家の深掘り問題が苦手な人向け:理論家の著作を読む
理論家の問題は、名前を知っているだけでは解けないものが多くなってきました。
その対策としてやってよかったのは、理論家関連の著作を読むこと。そもそも本が好きな人にはおすすめです。
全部読むと大変なので、目次をパーっと見て、気になるところを部分読みしていきます。すると、なんとなくその理論家のスタンスや大切にしていることが入ってくるので、初見の選択肢でも「いや、理論家の〇〇さんはそんなこと言わない気がする」というように判断がつくようになりました。
たとえば、以下の本を読みました。全部買うと高いのですが、Kindle unlimitedで0円で読めたり、図書館にあったりして助かりました。
クランボルツ
レビンソン
マズロー
ブリッジズ
シャイン
キャリアコンサルタント試験おすすめの勉強方法:論述編
論述は対策がしにくく、採点基準もよくわからないので困りますよね…
わたしなりに気を付けていたことを列挙します。
主訴は何か
→CLの感情、価値観が表れている発言を中心に、なるべく感情、価値観の言葉をそのまま使ってまとめる。
問題点は何か
→問題文を読みながら問題点を2つか3つピックアップし、問題点をまとめてから根拠としてどの発言を引用するか決める。よくある問題点は頭に入れておく(自己理解不足、仕事理解不足、情報不足、コミュニケーションの不足、自己効力感の低下など)
今後の展開
→問題点を考えるときに合わせて考えておく。いくつか問題点の選択肢があれば、方策が思いついているものをピックアップする。
解答用紙をダウンロードし、実際に書いてみることを繰り返しました。このくらいの文章を書くとだいたい一行使う、というのがわかってくるので、だんだん時間を測って、時間配分も自分のしっくりくるものを探します。
わたしの時間配分は下記の目安でした。
5分 問題を読む
10分 問1、2を回答
10分 問3、4の問題点と今後の展開を箇条書き(根拠のCL発言に下線)
15分 問3、4を回答
5分 予備
過去問の回答例はネットで公開されていますが、公式の模範解答が公開されていない以上、誰も正解を知らないので、「こう書くべき」という声に騙されず、自分が納得できる回答を仕上げることが重要だと思います。
慣れてくると自分なりの型ができてくるので、どんな問題でも何かしらは書ける!という自信がついてきます。
わたしの点数は、初回受験のキャリアコンサルティング協議会では32点、2回目のJCDAでは34点でした。何が良くて何が悪いのか、結果通知書を見てもわかりません。この試験のモヤモヤするポイントです。
養成講習の追加授業や有料の論述対策は受けるべきか?
ちなみに、養成講習や他の勉強会で有料の論述対策が紹介されるかもしれません。
わたしは利用しなかったですが、利用した人の話を聞いた印象では、別に答えがわかるわけでもないし、公式解答はない前提なのでモヤモヤは変わらないようです。
個人的には、受けなくてもいいのかなと思います。
キャリアコンサルタント試験おすすめの勉強方法:実技編
実技はさらに採点基準があいまいで、CL役や試験官との相性(当たり外れ)があるので対策が難しいです。
わたしは1回目が56点、2回目が64点でした。しかし、自分の準備度合、仕上がり度合は1回目を100とすると2回目が50くらいです。何を見ているのか、どう採点しているのか謎は深まるばかり…
勉強方法としては、ロープレをして録音したものを振り返る、というのをひたすらやっていました。Youtubeでもロープレ動画が上がっているので、適宜動画を止めながら、自分だったらなんと応答するか?をくり返し練習していました。
受験生の方と集まって練習するのもリアルで1回、オンラインで1回やりました。誰も正解がわからないのですが、質問のバリエーションや観点を増やす、口頭試問の練習ができるという意味で役に立ったと思います。
わたしなりに気を付けていたことを列挙します。
・来談目的をしっかり傾聴し、質問に困ったら来談目的に戻る
・ロープレ中は口頭試問や試験官のことを考えず、CLに集中する(話が聴けなくなるので)
・通常の会話よりゆっくり話す(緊張すると早口になりがち)
・口頭試問で沈黙を怖れない(考えがまとまってから話し始める)
あとは、当日やりきるだけ!という覚悟で乗り切るだけだと思います。論述・実技に関しては、準備量と結果が比例しない試験だと思っているので、ある程度の割り切り・開き直りが必要かもしれません。
養成講習の追加授業や有料の面接対策は受けるべきか?
わたしは受けなかったのですが、養成講習の最終日あたりで有料講座をおすすめされることがあります。
わたしが行った養成講習では当時7万円ほど。高いですよね。
養成講習に入る際、おそらく営業の方が「うちの養成講習を普通に勉強していたら合格レベルになるカリキュラムになっているので!」と自信満々に言っていて、まったく同じ人が最終日に「これを受けないと合格は厳しい」と言っていました。不信感が高まり、けして受けないぞと思ったのでした…
実際、高い講習を受けずに受かる人もいれば、受けて落ちる人もいます。そもそも運の要素もある試験なので(それが良くないのですが)、わざわざ落ちた時の傷を深くしなくてもいいかな、というのが個人的な意見です。
キャリアコンサルタント試験でやってよかったこと
その他、ちょっとしたことですが、やってよかったことを紹介します。
・一度はリアルで実技練習をしておく
最近はオンラインでロープレ練習をすることが多いと思いますが、全身見られている状態で、きちんとした服装でロープレをすることに一度は慣れておいたほうが良いと思います。
わたしは養成講習の代表ロープレに積極的に手を挙げるタイプだったので、そこで慣れたのもよかったです。その後もリアルでの練習を何度かしてから本番に臨みました。
・羽織るものを持っていく
7月の試験のときは、外は暑く、中は冷房がガンガン入っていて寒いという状況でした。上着など羽織るものを持っていきましょう。実技の控室も寒かったです。
・学科と論述の間に過ごす場所を探しておく
お昼を食べる場所、論述前まで過ごす場所のめどをつけておきます。ファミレスやカフェなどいくつか検索しておきましょう。会場が大学だと外のベンチなどで過ごせますが、天気が悪いと厳しいかもしれません。
・実技前、体調を万全にする
実技のときにのどを痛めていたり、咳が出ていたりすると大変です。実技前は体調第一、特にのどを痛めないように気を付けましょう。1週間前にのどを痛めて、本番までに治るかドキドキしました。当日ものど飴を持っていきました。
・自分の一番うまくできたロープレ録音を何度も聞く
ロープレ練習のときは録音をおすすめします。振り返りに使うのはもちろんですが、そのなかで自分なりに一番うまくいったものをくり返し聞くと、調子のよいときの自分の感覚をつかめます。うまい人のロープレを聞いても、所詮それは他人のロープレです。自分のロープレだからこそ、わたしはこのくらい聞けるという自信にもなります。
最後に
キャリアコンサルタント試験の勉強法を紹介しました。
正直、採点基準のあいまいさ、何が悪かったかわからない結果通知、受験料の高さ、養成講習のビジネスモデルなどモヤモヤするポイントが多い試験で、手放しでおすすめはできません。でも、受けると決めた方はぜひ最善を尽くしてほしいと思い、自分の経験をまとめてみました。
よい結果になることを願っています!
本業の会社員では研修講師やファシリテーターをしています。コーチングも提供しているので興味がある方はぜひご検討ください。
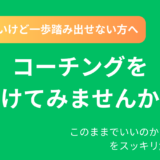 自分を信じて行動が続けられる方法:コーチングを受けてみませんか?
自分を信じて行動が続けられる方法:コーチングを受けてみませんか?

